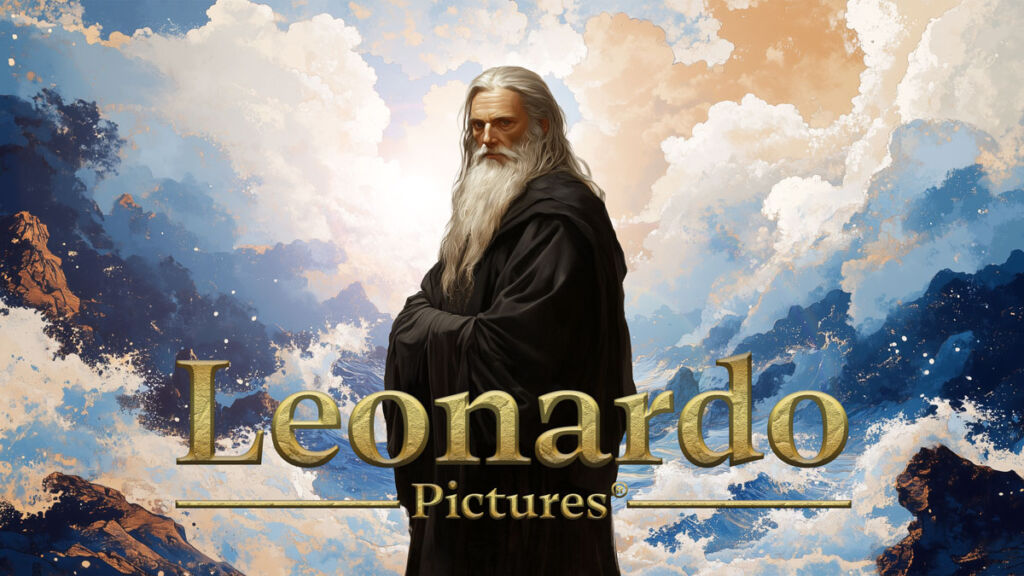戦略と共に、覇者への道を。
強い理由があれば、強い行動が生まれる
King John, シェイクスピア
μ(平均)↑・σ(ばらつき)↓の経営。AIが分散を抑え成果を平準化。
AGI・AI/生成AI/機械学習/データ科学✖️映像/AI研修


argmax_{π} 価値(創造性, 生産性), s.t. コンプライアンス/資源制約。 CEL × SDXが企業×AIのMDPを設計し、Post‑AGI成長へ収束。
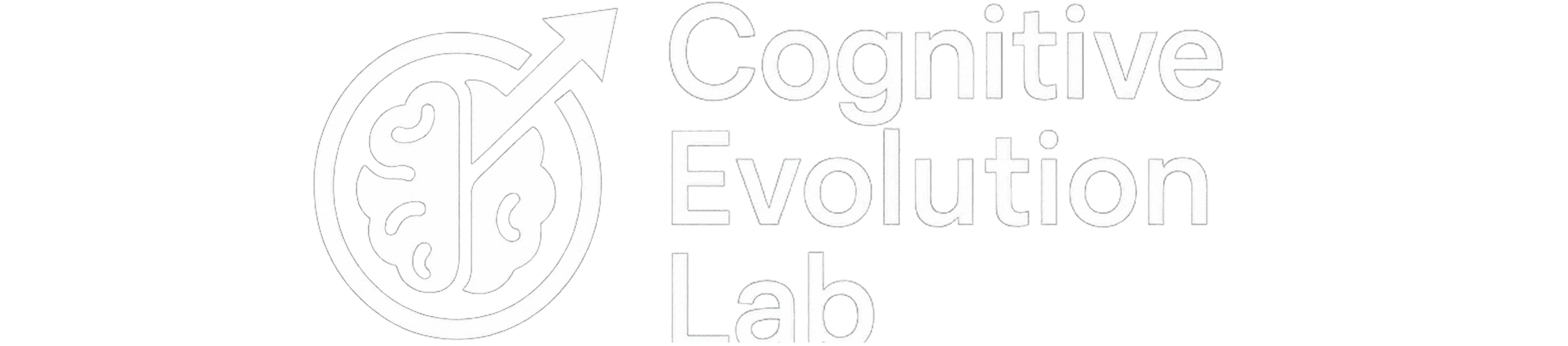

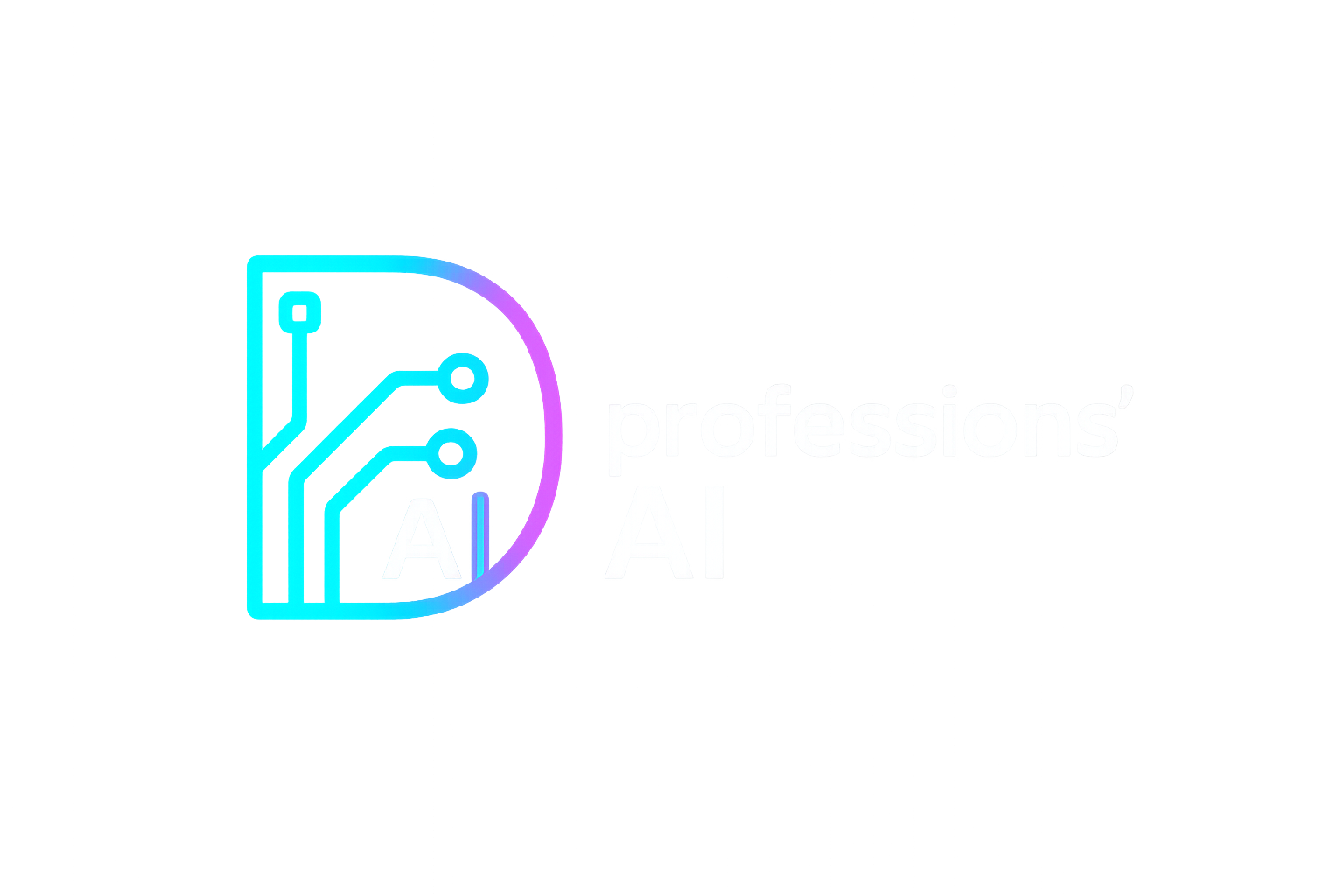
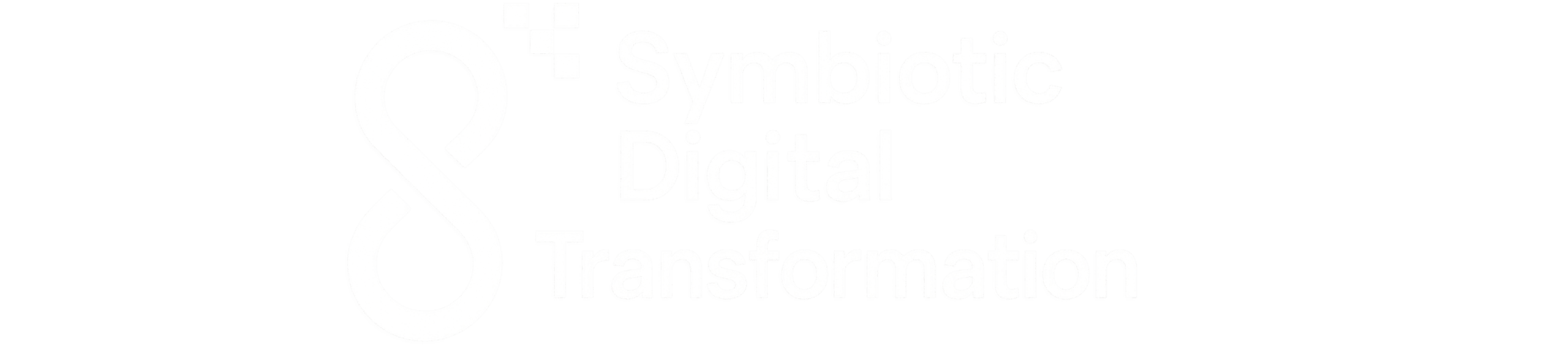

Leonardo Pictures®︎
感動 → 利益関数。
Leonardo Pictures®︎ が
AI‑professional Film™ で argmax(営業利益)。
マルチモーダル×多段推論 対応映像。
露出→視聴→商談化を閉ループ最適化。
感動を、営業利益に写像する力を。その手に。


Leonardo Pictures®︎
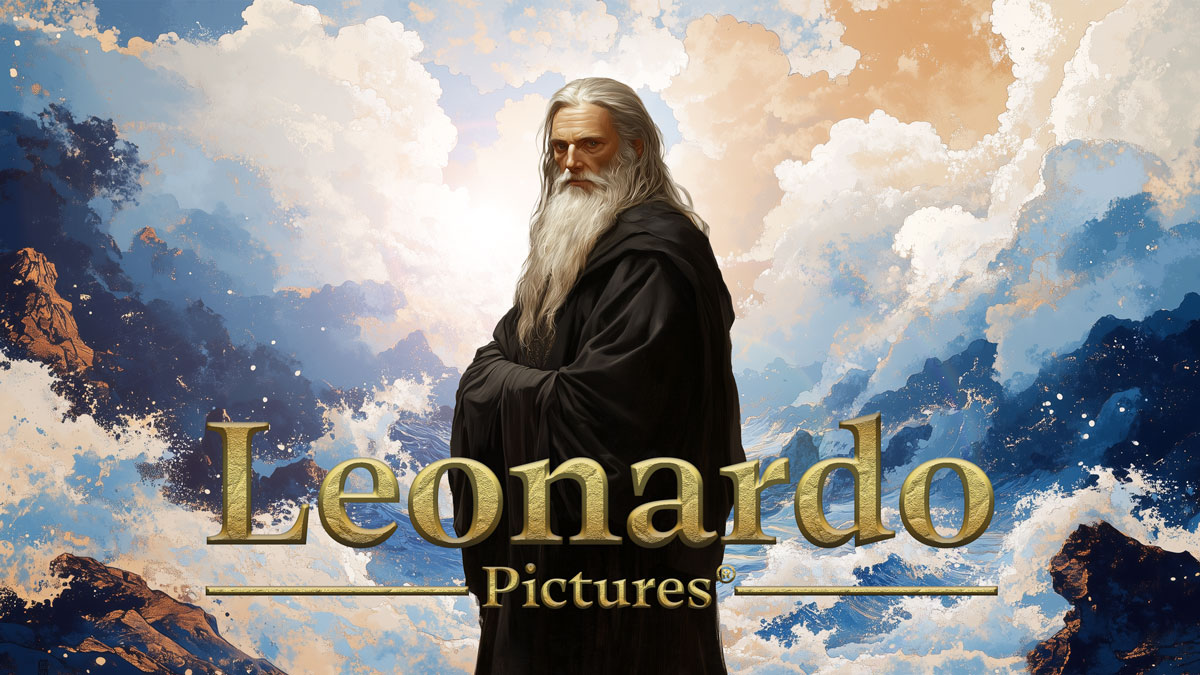
映像をナレッジグラフに接続された
検索資産へ転換し
Post‑AGI 時代の持続成長に収束させます。
AI‑professional Film™ は、AI Mode(多段推論 plan & verify × マルチモーダル理解)に最適化された映像設計フレームです。
映像内のテキスト・音声・画像・メタデータを同一コンテキストで整列し、時刻根拠/章立て/エンティティ同定/出典を付与。これにより検索AIが直接参照・要約・根拠提示できる「解釈可能な一次情報」として機能します。
Cognitive Evolution Lab × Symbiotic Digital Transformation の知見で、企業・法律事務所 × AI の相互強化ループ(計測→学習→投下→検証)を設計。
露出(Rich Result / Key Moments)→視聴→遷移→商談化→受注までをKPIツリーに分解し、閉ループ制御で μ(成果の平均)を上げ、σ(ばらつき)を下げる運用へ。
マーケティングや経営では、閉ループとは データ収集から改善までが循環している仕組み を指します。
例えば、顧客からのフィードバックを収集し → 分析し → 改善施策を実行し → その結果をまた評価する、という流れが一つのループとして完結する場合です。
Leonardo Pictures®︎ 支援例
1) AI‑professional Film™
章立てTOC(t₀..tₙ)/時間根拠つき要約/セクション間の因果リンク。
【AI 向け】台詞/テロップ/数値を機械可読に整形、字幕・オーバーレイに時刻・数値・出典を明示。
Key Moments / Rich Result への適合率↑(タイムコード・要約・实体タグ)。
目的は、argmax 〔視聴完走率 × CTR × CVR × 粗利〕 s.t. ブランド・法務。
2) AnswerClip™ Studio
想定質問 Top 50–200 を Q→Intent→Clip に写像、≤15秒の即答クリップを量産。
各Qに根拠カット(timestamp)を割当、字幕内に数値・出典を強制。
AIモード(AI Mode)/AI による概要/検索結果/SNSリールの即答スロットにフィット。
Qカバレッジ率(Recall@Q)、一次情報参照率、解決までのレイテンシ↓。
Leonardo Pictures ®︎ の 評価 KPIと目的関数
* \(v\):視聴率(再生/出現)
* \(c\):遷移CTR(クリック/再生)
* \(r\):CVR(商談・受任/遷移)
* \(m\):粗利(単価−変動費)
微分(改善余地の優先度) $$ \Delta \Pi \approx \frac{\partial \Pi}{\partial E}\Delta E + \frac{\partial \Pi}{\partial v}\Delta v + \frac{\partial \Pi}{\partial c}\Delta c + \frac{\partial \Pi}{\partial r}\Delta r + \frac{\partial \Pi}{\partial m}\Delta m - \Delta C $$ → AnswerClip は \(c\),\(r\) を、AI‑professional Film は \(E\), \(v\) を、CineGraph Link は \(E\),\(c\) と誤要約率(負の外部性)を主に押し上げます。
運用フレーム
* 方策更新:ベイズ/多腕バンディットで 探索–活用(ε) を自動調整。
* 制約条件:s.t.(法務・表現・ブランド一貫性・Pマーク等)。
* 安定化:μ↑・σ↓/Regret最小化/収束判定(効果サイズ & 事前停止)。
D professions' AI®︎

D professions' AI®︎ で
生成AI/意思決定アルゴリズム
を経営中枢へ実装し
「AI導入」を超える
「経営そのものの再設計(AI‑centric redesign)」を支援します。
主に、企業・法律事務所の経営者/経営弁護士/弁護士/取締役/経営企画/DXリーダー/AIプロジェクト統括CXO/次世代マネジャーを対象として支援をさせていただいております。
D professions’ AI®︎ のアプローチ
因果設計(データ→意思決定→成果)をKPIツリーに分解し
AI モード(ベクトル検索・類似度・Query Fan-Out(クエリ ファンアウト))に解ける情報設計
閉ループ運用(計測→学習→投下→検証)でμ(期待利益)を上げ、σ(ばらつき)を下げます。
経営の目的関数 Π(利益)を実運用で最大化する「継続アップデート可能な経営の仕組み」を提供します。
D professions’ AI®︎ は、生成 AI と意思決定アルゴリズムを経営の中枢に実装し、「AI を導入する」段階を超えて経営そのものを AI を中心に据えて再設計します。主に、企業および法律事務所の経営者や経営弁護士、弁護士、取締役、経営企画、DX リーダー、AI プロジェクトを統括する CXO、次世代マネジャーの方など、意思決定の現場に関わる方々を支援させていただいております。私たちは、データから意思決定、そして成果へと至る因果を KPI 木に分解し、ベクトル検索や類似度、Query Fan‑Out など AIモード(AI Mode) に「解ける」情報設計を施します。計測、学習、投下、検証の閉ループ運用で、期待利益の平均 μ を引き上げつつばらつき σ を抑え、経営の目的関数 Π(利益)を実運用で最大化する、継続アップデート可能な経営の仕組みを提供します。
D professions' AI®︎ 支援例
AIモード対策シミュレーション
AI検索(AIモード(AI Mode)・AIによる概要等)での解答候補化・ランディング誘導を最大化。
ベクトル検索/類似度/Query Fan-Out(クエリ ファンアウト) をNDCG@k / Recall@k / MRRで評価。
クエリ→意図→資産(ページ・動画・Q&A・構造化データ)の最適写像。
AI 検索における解答候補化とランディング誘導を最大化するために、クエリから意図、意図から自社資産(ページ、動画、Q&A、構造化データ)への写像を精密に設計します。ベクトル検索と類似度の指標、そして Query Fan-Out(クエリ ファンアウト) の展開を NDCG@k、Recall@k、MRR といったランキング評価で検証し、欠落領域を定量的に提示します。結果として、AIモード(AI Mode)・AI による概要(AI Overviews) に引用されやすい一次情報の構造化が前提化され、露出から遷移、そして商談化までの路線が一本化されます。
社内データの機械学習分析 × 経営ダッシュボード
需要・受注・LTV・離脱・在庫・稼働を回帰/分類/時系列で推定。
貢献度分解(SHAP等)で意思決定の説明可能性を担保。
粗利寄与、予測誤差(MAPE/RMSE)、利益曲線(Profit Curve)。
需要、受注、LTV、離脱、在庫、稼働といった業務変数を回帰・分類・時系列モデルで推定し、誤差は MAPE や RMSE で管理します。説明可能性は SHAP などの貢献度分解で担保し、各施策が粗利に与える寄与を利益曲線(Profit Curve)として可視化します。こうして見えたボトルネックに対し、勾配の大きい箇所から投資を振り向けることで、ΔΠ の回収速度を高めます。
法律事務所の受任予測と閾値最適化
モデル
ロジスティック回帰/勾配ブースティング+確率校正(Platt/Isotonic)。
目的
最適閾値(原則)
(Margin=期待売上−変動費)。
出力
案件スコア、優先接客リスト、チャネル別配分。
受任確率はロジスティック回帰や勾配ブースティングで推定し、Platt あるいは Isotonic による確率校正で意思決定に使える数値へ整えます。目的は、
を満たすことにあり、収益マージンに基づく最適閾値の原則は
によって与えられます。結果として、案件スコアと優先接客リスト、そしてチャネル別の配分方針が一貫したロジックで提示されます。
広告配分の数理最適化
問題設定
s.t.
推定
チャネル反応関数
を Diminishing Return で近似(例:
解法
凸緩和/勾配法/多腕バンディット(UCB/TS)で探索–活用を自動調整。
配分の問題は maxb≥0∑jProfitj(bj) という形で定式化し、総予算 ∑jbj≤B とチャネル上限 bj≤capj の制約のもとで解きます。チャネル反応関数 Profitj(b) は逓減収益を仮定した αjlog(1+βjb) などで近似し、凸緩和や勾配法、多腕バンディット(UCB/Thompson)を用いて探索と活用の割合を自動調整します。これにより、短期の回収と長期の学習が衝突せず、動的な最適点へ収束します。
配信時間・稼働最適化
目的
時間帯×媒体×事件種で受任率ピークに資源をアロケーション。
手段
時系列分解+制約付き最適化(人員・SLA・ブランドs.t.)。
時間帯、媒体、事件種を掛け合わせた反応ピークを時系列分解で抽出し、人的稼働や SLA、ブランド基準といった制約 s.t. を明示したうえでアロケーションを設計します。広告投下のタイミングを受任率の山に合わせることで、同一予算でも実質的な受任ロスを削減できます。
【法律事務所 向け】受任最大化の数理
閾値最適化・広告配分・時間配信・受任予測を閉ループで回し、
μ(期待利益)を上げ σ(ばらつき)を下げる運用へ安定収束。
単月の利益は
と表せます。
ここで は受任確率、は単価、は変動費、 は獲得コスト、は応対の閾値です。
期待利益を最大化するための基本則は であり、予測確率が 以上の案件に注力すると、同一稼働でも粗利が押し上がります。チャネル別に見る場合は を用い、媒体ごとのプライオリティを決めます。
モデルの運用では、案件属性やマーケ指標、稼働変数を統合し、リーケージを防ぎながら学習します。評価は AUC や Lift のみならず Profit Curve や Incremental ROI を併用して意思決定に落とし込み、PSI や KS によるドリフト監視で自動リトレーニングを回すことで、精度と収益の両面で陳腐化を抑えます。
目的関数(単月)
閾値設計
(1)最適閾値
予測確率
の事件案件を積極対応 ⇒ 期待利益最大化。
(2)チャネル別
で配分の優先度を決定。
モデル運用の要点
(1)データ設計
案件属性+マーケ指標+稼働変数を統合、リーケージ防止。
(2)評価
AUC/Liftに加えProfit Curve / Incremental ROIを採用。
(3)校正
確率校正で利益最大化の閾値が実数値化。
(4)再学習
ドリフト監視(PSI/KS)→自動リトレで陳腐化抑制。
運用フレーム(評価・最適化)
KPI の流れは、露出 から訪問 、相談 、受任 、そして粗利 へと続き、全体の利益は
として分解可能です。
運用はまず計測から始まり、時刻根拠と出典を持つイベントを定義してデータ品質を確保します。次に因果推論と機械学習、特に確率校正を通じて学習し、続いてポリシー反復や多腕バンディットで配分や閾値、クリエイティブを更新します。
検証はベイズ AB と連続モニタリングで早期停止を可能にし、法務やブランド一貫性、個人情報、SLA といった制約条件のもとで安全に運用します。
ダッシュボードには KPI 分解と収益寄与、分散や下方 CVaR などのリスク指標、さらに Regret の推移を並べ、特徴量寄与やカバレッジ、外挿検知といった説明可能性指標で監査性を保ちます。